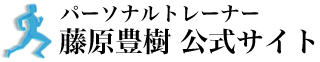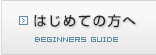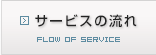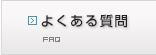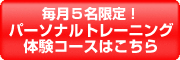藤原トレーナー直伝コラム - 王道パーソナルトレーナー藤原豊樹
運動は肉体の老化を遅らせることができる。
2014年06月10日 [記事URL]
運動の効果は健康面で、
良い影響を与えるのは言うまでもありません。
アンチエイジング効果を謳う場合もありますが、
中高齢者にとっては老化現象を遅らせることができます。
ただし、老化は止めることはできません。
肉体の老化現象を以下に記します。
30歳以降は筋力が年1、2%ずつ減少します。
(上半身よりも下半身の筋力の方が早く衰えます。)
40歳を過ぎると、骨密度が年々0.5%ずつ低下します。
とくに女性の場合、閉経後は年間2〜3%骨密度が低下してしまいます。
30代頃から徐々に体脂肪(とくに内臓脂肪)が増えていきます。
高齢となると、バランス感覚の悪化や反応が鈍くなったりします。
関節も硬くなるため、柔軟な動きができなくなり、転倒もしやすくなります。
喉の渇きを感じにくくなり、水分を蓄える機能も衰えるので、
脱水症状になりやすくなります。
中高齢者の人ほど、
夏は運動をしていなくても積極的な水分補給が必要です。
最大心拍数が減り、一回で拍出される血液量も減ります。
また酸素を取り込む能力も衰えますので、
長時間の運動を続けることが難しい体となっていきます。
(最大酸素摂取能力は10年ごとに約10%近く減少してしまいます。)
運動を開始しても、
体が運動に適応するまの時間が長くなります。
したがって、
年齢が高い人ほど入念なウォーミングアップが大切になります。
と、以上までにしておきます。
年齢と重ねるごとに様々な老化現象が起こりますが、
定期的に運動を続けていくことで遅らせることができます。
高齢者にとっては、体を衰えないようにする。
つまり変わらないようにすることが大事だと思います。
運動の方法としては、
筋トレや有酸素運動が有効です。
特別な器具や方法も用いなくても、
1日に階段を10階くらい登るだけでも良いと思います。
(一度に10階も登る必要はありません。)
運動を積極的に続けることで、
脳へ送られる血液の循環が良くなり認知症の予防にもなるでしょう。
ただ運動しない人ほど、
年を重ねるごとに関節が痛みが増す場合があります。
運動後の飲酒は悪影響か?
2014年06月03日 [記事URL]
運動・トレーニングをした後に、飲酒による悪影響があるか無いかは飲む量によります。
各個人の体質・体重にもよりますが、2〜3杯の飲酒であれば、翌日のトレーニングに悪影響はありません。
ただし、それ以上の飲酒になると筋肉の回復及び、体内の栄養補給が阻害されてしまいます。
アルコールの摂取量が多くなると、中枢神経系に影響を及ぼすために脳から筋肉への命令が伝わりにくくなるからです。
よってトレーニング後に大量の飲酒をした場合は、トレーニング効果が期待できなくなってしまいます。
選手(アスリート)が飲み会に参加する場合は、翌日のためにも当日のトレーニングを控えるか軽めに済ますことが得策です。
また夏場の場合は、脱水症状を軽減するため酒と水を交互に飲むなどチェーサーを準備しておくことも良いでしょう。
体調不良(風邪)の時の運動のしかた
2014年06月03日 [記事URL]
原則として、
体調不良の時や風邪をひいている時は運動すべきではありません。
ですが、
体調に異変を感じながらも運動ができないほどでは時もあるでしょう。
そのような状態の時に、
運動をすると気分がスッキリ良くなる場合もありますが、
それは運動によって気道や血の巡りが良くなったからだと思えることもあります。
中強度の運動は免疫機能を向上させる効果がありますが、
結局のところは安静が一番です。
体調不良の時は体がその原因に対して働いているので、
余計な体力を消耗しない方が良いと思います。
ただ日常的に運動・トレーニングを課せられているアスリートの場合、
風邪などを起こした時に、
どのくらいの運動なら体に悪影響を及ぼさないのか知りたいところでしょう。
鼻水やくしゃみ、
喉の痛みくらいであれば、
軽い運動に留めておいた方が無難です。
発熱や筋肉痛、
咳などの症状が出ている時は、
安静に過ごすべきです。
したがって、
風邪のときの運動は症状に悪影響を及ぼす可能性が少なく、
回復を早める場合もあるとされますが、
いずれにせよ軽い運動に留めていた方が無難です。
長距離レースからの回復時間は?
2014年05月04日 [記事URL]
マラソン、トライアスロン、自転車などの長距離レースに参加すると、回復には時間がかかります。
レースの時よりも、
肉体的に辛いとされる場合もあるほどです。
筋肉痛は、
レース翌日から普段の生活で分かりやすい面があります。
しかし、
数時間の高い心拍数を続けたた心筋、
また免疫システムの回復には1週間程度を要します。
さらに骨格筋の疲労回復には数週間を要する場合もあります。
これには神経筋の疲労が大きく影響しているためだと考えられています。
レースは十分な休養が必要ですが、全く動かない状態をつくるより、徐々に体を動かす方が良いでしょう。
レース後は3日間ほど休養し、
その後は2週間を目安に徐々に元のトレーニング量に戻すの良いです。
ただ大事なのは体調に合わせて柔軟に対応すべきです。
マッサージは疲労物質を除去しない。
2014年05月04日 [記事URL]
マッサージを受けて身体が軽くなった、
楽になったと感じる方は多いと思います。
しかし生理的な効果か、
ブラシーボ効果なのか難しいところです。
疲労の原因は、
乳酸が溜まっているからだとされてしまう場合があります。
そこで乳酸を取り除くために血流量を促進させようと試みるでしょう。
そこで血行を良くするためにマッサージを受ける方がいますが、
手の動きで筋肉などの組織が圧迫されてしまって血行は改善されません。
疲労回復にマッサージが常に正しい方法であることは言えません。
したがって、
身体の血行の促進するには自ら身体を積極的に動かす方が効果的であります。
温熱療法は体の痛みは和らげるか?
2014年05月04日 [記事URL]
身体を温めることで筋肉痛が和らいだり、
慢性的な痛みを患っていた部位の柔軟性が高まるといった経験をお持ちではないでしょうか?
ケガをした直後は冷やさなければなりませんが、
温熱処方をすることによってある程度の効果はできます。
しかし、
動くことが困難な状態では温熱療法は効果的ですが、
身体の表面部分にしか効果を期待できません。
動くことが困難でない限りは、
やはり一般的な準備運動がして身体を温めるのに最も効果的です。
やはり適切なウォーミングアップが大事であるということです。
運動後に冷水風呂に入ることで疲労は回復しやすいか?
2014年04月22日 [記事URL]
疲れた時ほど、温かい風呂に浸かることで新陳代謝が活発化します。
そして、素早く老廃物を促す効果があるとされています。
しかしスポーツ選手では、運動後に冷たい水風呂に入ります。
筋肉の細微な炎症を抑える効果があるとされているからです。
運動後に水風呂に入ると血管が収縮するので、損傷した部位に溜まった老廃物を早く排出する効果があるのです。
風呂から上がると冷えた部分が再び暖まると、新鮮な血液が流れ込んで治療を促進するというわけです。
しかし、今のところ明確な研究報告はされていません。
ですが、ケガをした直後は患部を冷やすことは有効とされているので、ある程度の効果は期待できるかもしれません。
怪我(挫傷)をした時の現場での処置(RICE)
2014年04月17日 [記事URL]
怪我(挫傷)を最小限にする現場での救急処置としてはRICE処置が適切であるとされています。
RICEとは、Rest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫) 、Elevation(挙上)のそれぞれの頭文字を合わせた言葉です。
怪我をしてしまった直後は、RICE処置を行うことによって、患部の痛みを和らげ、出血や腫れなどを抑える効果があります。
RICE処置をしたことで、その後の回復に好影響を与えることができます。
ただRICE処置は医師の診察を受けるための現場でできる措置であります。
RICEだけで済ませず医師の患部を診てもらうことが必要です。
運動やスポーツをする現場では、氷などを用意しておくことが望ましいでしょう。
また氷は外傷時以外の時でも役立ちます。
RICE処置には以下のことを注意して行って下さい。
1.氷冷は就寝時(患部を心臓より高く挙げる)以外、24〜48時間繰り返し行う。
2.1回の氷冷につき20〜30分程度が安全かつ効果的。
3.氷冷の間隔は約1時間程度が目安。
4.RICE処置中は湿布を貼らない。飲酒及び入浴も禁止である。
怪我(捻挫)の回復を早めるには
2014年04月17日 [記事URL]
怪我をした直後の晴れや痛みが終わった後は、少しでも患部を動かす方が回復は早まります。
一般的には安静が第一とされます。
しかしスポーツ選手においては、長期間の完全休養は逆効果なのです。
回復が早まるどころか、むしろ長引いて再発を招く可能性もあります。
全く動かないで治療することは、筋肉とそれに関係する組織が弱くなってしまうのです。
早く復帰するためには、まずケガを動かした直後はRICE処置を行います。
その後、腫れや痛みが軽減すれば、徐々に無理のない範囲(痛みを目安)で動かすべきです。
もちろん動かした後のケアとして患部を冷やして、休むときは患部を心臓より高く挙げて下さい。
痛みを伴うほど動く必要はありません。
しかし患部をかばい過ぎて回復を遅らせないようにしましょう。
体幹トレーニングで、どこの筋肉を鍛えるべきか?
2014年03月28日 [記事URL]
最近では、体幹がクローズアップされています。
しかし、体幹に関わる筋肉はどれか?
これについては意見がバラバラです。
体幹を安定させてパフォーマンス向上に役立てたり、ケガの予防に役立てるため重要な筋肉とは?
それはまず、お尻の筋肉(臀部)、お腹の筋肉(腹筋の深層部)、腰椎と大腿骨を結ぶ腸腰筋が重要になります。
背筋や骨盤まわり、腹筋などが重要だと思われがちですが、腹筋が割れていたり、腰回りが絞り込まれいるから体幹が安定しているわけではありません。
腹筋の深層部と腸腰筋を鍛えるには、仰向けに寝た状態で胴体を動かさず両脚を伸ばしたまま45度の状態で維持することです。
ボディコンサルティング
藤原豊樹
住所:〒157-0067
東京都世田谷区喜多見4-3-15
電話:03-5315-9477
Copyright© 2023 王道パーソナルトレーナー藤原豊樹 All Rights Reserved. ![]()